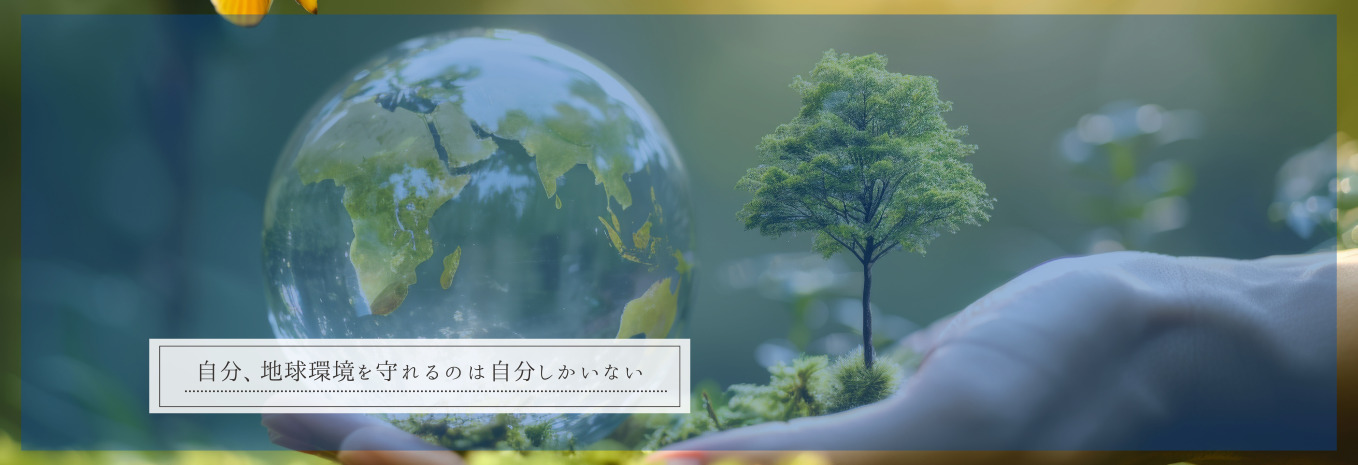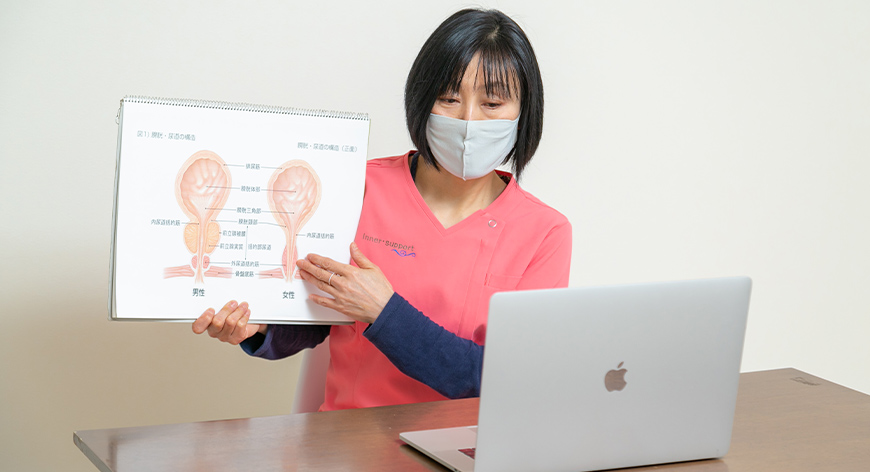
恥ずかしくて人にはなかなか相談出来ない「尿トラブル」問題。なんでだろう?どうしたらいいの?の不安・心配を原因と対策を理解して取りのぞきましょう!
尿トラブルはなぜ起きるか?
こちらでは、尿トラブルの原因とトレーニングについてご説明いたします。
骨盤底筋がゆるんで弱ってくると
骨盤底筋がゆるんで弱ると、下記のような現象が起こります。
①尿を出そうとする力に尿道を締めつける力が耐えられなくなり、尿漏れが起こる。
②支える力が弱まると膀胱が下垂し、尿道の長さが短くなる・収縮して、尿道を締め押しつぶす力がかかりにくくなる。
③膀胱のいちばん底の部分にある副交感神経の神経末端が、尿が膀胱に十分たまらないうちから活性化し、排尿を我慢できなくなる。
オーストラリアの女性泌尿器科医ピーター・パパ・ペトロス先生は以下のようにおっしゃっています。
「女性の頻尿や尿漏れなどの尿トラブルは、すべて骨盤底の筋肉や靭帯の弱まりやゆるみなどの【骨盤底機能】から説明できる」
①尿を出そうとする力に尿道を締めつける力が耐えられなくなり、尿漏れが起こる。
②支える力が弱まると膀胱が下垂し、尿道の長さが短くなる・収縮して、尿道を締め押しつぶす力がかかりにくくなる。
③膀胱のいちばん底の部分にある副交感神経の神経末端が、尿が膀胱に十分たまらないうちから活性化し、排尿を我慢できなくなる。
オーストラリアの女性泌尿器科医ピーター・パパ・ペトロス先生は以下のようにおっしゃっています。
「女性の頻尿や尿漏れなどの尿トラブルは、すべて骨盤底の筋肉や靭帯の弱まりやゆるみなどの【骨盤底機能】から説明できる」
『骨盤底筋』を弱める原因
①妊娠・経膣出産
妊娠中は大きくなった子宮を支えるため、骨盤底筋に大きな負担がかかっています。さらに、女性の身体は出産に備えて関節や関節の結合部がゆるんでいくこともあり、このことが原因で妊娠中の尿もれは起こります。また、経膣分娩は赤ちゃんの頭がお母さんの骨盤の大きさの限界近くまで成長するため、どうしても出産時に骨盤底筋が傷つきやすくなります。だいたい産後1年以内によくなるのですが、中には損傷が大きかった方や骨盤底筋の弱さが潜在的に残ってしまう方もいます。
②加齢(ホルモンの減少)
閉経などで女性ホルモン(エストロゲン)の減少とともに、筋肉量が減り骨盤底筋の弾力が落ちてきます。さらに、筋肉結合組織やグルコサミノグリカン、※エラスチン線維、コラーゲンなどの影響を受けます(※エラスチンとは、主にコラーゲン同士を結びつける働きを持つ繊維状のたんぱく質です。皮膚の真皮や血管、靭帯などに存在し、肌にハリや弾力を与えたり、血管や靭帯の柔軟性・伸縮性を維持しています)。加齢に伴うエラスチンの喪失は、重力の影響で骨盤底筋組織を「だらり」とさせ、全体の張力を60%に減少させてしまいます。排泄は 自律神経と深い関わりがあるため、自律神経の調整がうまくいかなくなることで頻尿になっている方が多いと考えられます。
③便秘・強い腹圧・肥満
便秘がちで毎日何分もトイレでいきんだり、強い腹圧(咳・くしゃみ)などは、骨盤底筋のダメージを加速させてしまいます。試しにご自身の恥骨の少し上に手を置き、軽くせき込んでみてください。腹圧の強さを感じていただけると思います。また、肥満はお腹や腰にたまった脂肪が上からのしかかって圧をかけるので、膀胱を押し下げる形となり悪化させてしまう原因になります。
妊娠中は大きくなった子宮を支えるため、骨盤底筋に大きな負担がかかっています。さらに、女性の身体は出産に備えて関節や関節の結合部がゆるんでいくこともあり、このことが原因で妊娠中の尿もれは起こります。また、経膣分娩は赤ちゃんの頭がお母さんの骨盤の大きさの限界近くまで成長するため、どうしても出産時に骨盤底筋が傷つきやすくなります。だいたい産後1年以内によくなるのですが、中には損傷が大きかった方や骨盤底筋の弱さが潜在的に残ってしまう方もいます。
②加齢(ホルモンの減少)
閉経などで女性ホルモン(エストロゲン)の減少とともに、筋肉量が減り骨盤底筋の弾力が落ちてきます。さらに、筋肉結合組織やグルコサミノグリカン、※エラスチン線維、コラーゲンなどの影響を受けます(※エラスチンとは、主にコラーゲン同士を結びつける働きを持つ繊維状のたんぱく質です。皮膚の真皮や血管、靭帯などに存在し、肌にハリや弾力を与えたり、血管や靭帯の柔軟性・伸縮性を維持しています)。加齢に伴うエラスチンの喪失は、重力の影響で骨盤底筋組織を「だらり」とさせ、全体の張力を60%に減少させてしまいます。排泄は 自律神経と深い関わりがあるため、自律神経の調整がうまくいかなくなることで頻尿になっている方が多いと考えられます。
③便秘・強い腹圧・肥満
便秘がちで毎日何分もトイレでいきんだり、強い腹圧(咳・くしゃみ)などは、骨盤底筋のダメージを加速させてしまいます。試しにご自身の恥骨の少し上に手を置き、軽くせき込んでみてください。腹圧の強さを感じていただけると思います。また、肥満はお腹や腰にたまった脂肪が上からのしかかって圧をかけるので、膀胱を押し下げる形となり悪化させてしまう原因になります。
女性の身体について
骨盤内では、靭帯が膀胱・子宮・直腸を引っ張り支えています。骨盤底筋は前への張力(恥骨尾骨筋)、後への張力(挙筋板)、下への張力(肛門周囲縦走筋)の3方向でバランスを保っています。そのバランスが崩れることで、尿漏れや臓器脱などの症状が現れるのです。
バランスのとれた「骨盤底筋」は、腹圧がかかっても尿道口へ締める指令がうまく伝わって漏れることはありません。しかし「骨盤底筋」がぐらぐらに弱まり、たるんだ状態になると、腹圧がかかったときに尿道口を締める指令がうまく伝わらず、尿道口が締まり切らないため漏れてしまいます。ゆるゆるになった尿道口にコラーゲンを注入する治療方法もありますが、完治は難しいと思われます。
女性の尿道は男性に比べると太くて短く、長さはおよそ3~5㎝くらい。この女性特有の形状が、不意に腹圧がかかると尿漏れしやすい原因となります。若い女性に多い「冷え症」や中年以降の「中年太り」の要因の一つにもなっています。さらに、女性の大きな身体的変化や閉経期も影響が。
女性ホルモンは 、月経・妊娠のコントロール以外に骨量の維持・自律神経の安定・記憶力の維持など重要な働きを担っています。
男性ホルモンは 一生の間の分泌量はあまり変化がなく高齢期に徐々に減少しますが、女性ホルモンは閉経前後は急激に減っていきます。女性ホルモンの分泌量が減少すると筋肉が弱りやすくなり、膀胱・膣が萎縮し、たんぱく質の合成する力も衰えるため、身体の健康状態を維持することが難しくなるのです。
このように、女性は尿トラブルがあって当たり前な状況にあります。
トラブルになる前に正しい知識を持ち、予防・改善のための取組みを日常生活に取り入れてください。
バランスのとれた「骨盤底筋」は、腹圧がかかっても尿道口へ締める指令がうまく伝わって漏れることはありません。しかし「骨盤底筋」がぐらぐらに弱まり、たるんだ状態になると、腹圧がかかったときに尿道口を締める指令がうまく伝わらず、尿道口が締まり切らないため漏れてしまいます。ゆるゆるになった尿道口にコラーゲンを注入する治療方法もありますが、完治は難しいと思われます。
女性の尿道は男性に比べると太くて短く、長さはおよそ3~5㎝くらい。この女性特有の形状が、不意に腹圧がかかると尿漏れしやすい原因となります。若い女性に多い「冷え症」や中年以降の「中年太り」の要因の一つにもなっています。さらに、女性の大きな身体的変化や閉経期も影響が。
女性ホルモンは 、月経・妊娠のコントロール以外に骨量の維持・自律神経の安定・記憶力の維持など重要な働きを担っています。
男性ホルモンは 一生の間の分泌量はあまり変化がなく高齢期に徐々に減少しますが、女性ホルモンは閉経前後は急激に減っていきます。女性ホルモンの分泌量が減少すると筋肉が弱りやすくなり、膀胱・膣が萎縮し、たんぱく質の合成する力も衰えるため、身体の健康状態を維持することが難しくなるのです。
このように、女性は尿トラブルがあって当たり前な状況にあります。
トラブルになる前に正しい知識を持ち、予防・改善のための取組みを日常生活に取り入れてください。
尿トラブルの種類
①腹圧性尿失禁
成人女性の3~5人に1人の割合で悩んでいるといわれています。女性は誰でも咳やくしゃみ、大笑いしたとき少し尿が漏れる経験が一度くらいあって正常です。一般に、腹圧性尿失禁は40代後半以降の女性に多いトラブルです。
【特徴】
●咳やくしゃみなど、腹圧で漏れたことがある
●寝ているときや座っているときは漏れない
②切迫性尿失禁
【特徴】
●突然強い尿意をもよおし、我慢できなくなる
●水の音を聞いたときやドアノブに手をかけたときなど、強い尿意が突然おこる
●突然の強い尿意でトイレまで間に合わず漏れてしまう
③溢流性尿失禁
膀胱が膨らんでいるので、下腹部が張って外見からも出ているのが分かります。これは、排尿がうまく行われず尿が膀胱からあふれて漏れてしまっている状態です。このため、尿路感染症が起こりやすくなったり、腎臓から膀胱への流れが妨げられることで腎不全となることもあるため、早めに医師に相談することが肝心です。
【特徴】
●トイレでなかなかおしっこがでない
④反射性尿失禁
排尿に関係している機能に直接の問題があるのではなく、それ以外の心身の機能に何かしらの障害(体運動機能の低下や認知症など)があり、それが原因で尿失禁を起こしてしまいます。
【特徴】
●尿失禁後も気がつかない
●トイレを探せず失禁してしまう
●トイレでないところで失禁してしまう
⑤機能性尿失禁
【特徴】
●常に本人の意志とは関係なく尿が出てしまう
●膀胱に尿がたまってもわからない
●尿意がないのに、一気に大量の尿を失禁してしまう
⑥過活動膀胱
膀胱が過剰に活動してしまう病気です。
【特徴】
●尿意の切迫感と、昼夜をとわない頻尿
成人女性の3~5人に1人の割合で悩んでいるといわれています。女性は誰でも咳やくしゃみ、大笑いしたとき少し尿が漏れる経験が一度くらいあって正常です。一般に、腹圧性尿失禁は40代後半以降の女性に多いトラブルです。
【特徴】
●咳やくしゃみなど、腹圧で漏れたことがある
●寝ているときや座っているときは漏れない
②切迫性尿失禁
【特徴】
●突然強い尿意をもよおし、我慢できなくなる
●水の音を聞いたときやドアノブに手をかけたときなど、強い尿意が突然おこる
●突然の強い尿意でトイレまで間に合わず漏れてしまう
③溢流性尿失禁
膀胱が膨らんでいるので、下腹部が張って外見からも出ているのが分かります。これは、排尿がうまく行われず尿が膀胱からあふれて漏れてしまっている状態です。このため、尿路感染症が起こりやすくなったり、腎臓から膀胱への流れが妨げられることで腎不全となることもあるため、早めに医師に相談することが肝心です。
【特徴】
●トイレでなかなかおしっこがでない
④反射性尿失禁
排尿に関係している機能に直接の問題があるのではなく、それ以外の心身の機能に何かしらの障害(体運動機能の低下や認知症など)があり、それが原因で尿失禁を起こしてしまいます。
【特徴】
●尿失禁後も気がつかない
●トイレを探せず失禁してしまう
●トイレでないところで失禁してしまう
⑤機能性尿失禁
【特徴】
●常に本人の意志とは関係なく尿が出てしまう
●膀胱に尿がたまってもわからない
●尿意がないのに、一気に大量の尿を失禁してしまう
⑥過活動膀胱
膀胱が過剰に活動してしまう病気です。
【特徴】
●尿意の切迫感と、昼夜をとわない頻尿
膀胱コントロール
膀胱には200~400mlくらいの尿をためる機能があり、人間はこのたまった尿を1日に5~7回排泄するといわれています。
膀胱は風船のようなものです。適切な量の尿をしっかりためて、それをゆっくり排尿する。「膀胱のストレッチ」でやわらかくよく伸びるようにして、膀胱機能をよい状態に保ちましょう。
「尿意を我慢したら膀胱炎になる」と思っている方が多くいらっしゃいますが、実はこれは誤解です。膀胱炎にならない予防法は、膀胱に尿をためないことではなく、ストレスをためないよう心身の過労を防ぎ、免疫力を維持することです。
医師から止められている方以外は【膀胱コントロール】を行い、1日の排尿回数が5~7回くらいになるようセルフコントロールすることをおすすめします。
膀胱は風船のようなものです。適切な量の尿をしっかりためて、それをゆっくり排尿する。「膀胱のストレッチ」でやわらかくよく伸びるようにして、膀胱機能をよい状態に保ちましょう。
「尿意を我慢したら膀胱炎になる」と思っている方が多くいらっしゃいますが、実はこれは誤解です。膀胱炎にならない予防法は、膀胱に尿をためないことではなく、ストレスをためないよう心身の過労を防ぎ、免疫力を維持することです。
医師から止められている方以外は【膀胱コントロール】を行い、1日の排尿回数が5~7回くらいになるようセルフコントロールすることをおすすめします。
膀胱トレーニング
頻尿のお悩みをもつ方はもちろん、頻尿気味と感じる方すべてに必要なトレーニングです。
一般的に尿漏れ体験のある人は、尿に対する不安から早め早めにトイレに行くクセがついています。つまり、頻尿傾向になっているのです。すると知らないうちに膀胱の感覚が過敏になり、たくさんの尿をためることができなくなることでさらに頻尿が悪化してしまいます(どんなに排尿間隔が短くても、本人が気にならないのであれば問題はありません。あくまで本人が不便に感じていることがポイントになります)。
「なんだか最近トイレが近くてイヤだな」と感じたら膀胱トレーニングを行ってみてください。
切迫性尿失禁、あるいは混合型尿失禁の方の場合、膀胱トレーニングで70~90%の方が改善したと感じることができるそうです。
【膀胱トレーニングとは?】
『会陰排尿筋抑制反射』を使います。
尿道括約筋を締めると、収縮した刺激により副交感神経が働き、脊椎内の排尿中枢に信号として送られます。ここから膀胱に対して「異常な収縮を抑えるように」という信号が送られ、強い尿意が抑えられる…これを『会陰排尿筋抑制反射』といいます。
【トレーニング方法】
●尿意を感じたときは、尿道括約筋を締めながら何か別のことに意識を集中してみてください。強い尿意の波を乗り越えたあと「まだトイレに行きたいな」という感覚が残っていたら、そこで初めてトイレに行くようにしましょう。
●「トイレに行きたい」と尿意が起こったらまず5分くらい我慢してみます。最初は1日数回でOKです。
まずは約1週間くらい続けてみてください。最初からギリギリまで我慢する必要はありません。ご自身ができる範囲で十分です。
1週間くらいして無理なくできるようになったら、さらに5分ほど我慢してトレーニングを続けてみましょう。外出先などでは難しいと思いますので、自宅でご自身が一番楽にできるタイミングからはじめてみてください。
自信がついてきたら、少しずつ回数や時間を増やし、無理のない範囲内でゆっくり継続していきましょう。数ヶ月かけて排尿間隔が2~3時間に維持できるようになれば、トイレのことで悩む回数も減っていきます。ご自身の膀胱の機能を信じましょう。
一般的に尿漏れ体験のある人は、尿に対する不安から早め早めにトイレに行くクセがついています。つまり、頻尿傾向になっているのです。すると知らないうちに膀胱の感覚が過敏になり、たくさんの尿をためることができなくなることでさらに頻尿が悪化してしまいます(どんなに排尿間隔が短くても、本人が気にならないのであれば問題はありません。あくまで本人が不便に感じていることがポイントになります)。
「なんだか最近トイレが近くてイヤだな」と感じたら膀胱トレーニングを行ってみてください。
切迫性尿失禁、あるいは混合型尿失禁の方の場合、膀胱トレーニングで70~90%の方が改善したと感じることができるそうです。
【膀胱トレーニングとは?】
『会陰排尿筋抑制反射』を使います。
尿道括約筋を締めると、収縮した刺激により副交感神経が働き、脊椎内の排尿中枢に信号として送られます。ここから膀胱に対して「異常な収縮を抑えるように」という信号が送られ、強い尿意が抑えられる…これを『会陰排尿筋抑制反射』といいます。
【トレーニング方法】
●尿意を感じたときは、尿道括約筋を締めながら何か別のことに意識を集中してみてください。強い尿意の波を乗り越えたあと「まだトイレに行きたいな」という感覚が残っていたら、そこで初めてトイレに行くようにしましょう。
●「トイレに行きたい」と尿意が起こったらまず5分くらい我慢してみます。最初は1日数回でOKです。
まずは約1週間くらい続けてみてください。最初からギリギリまで我慢する必要はありません。ご自身ができる範囲で十分です。
1週間くらいして無理なくできるようになったら、さらに5分ほど我慢してトレーニングを続けてみましょう。外出先などでは難しいと思いますので、自宅でご自身が一番楽にできるタイミングからはじめてみてください。
自信がついてきたら、少しずつ回数や時間を増やし、無理のない範囲内でゆっくり継続していきましょう。数ヶ月かけて排尿間隔が2~3時間に維持できるようになれば、トイレのことで悩む回数も減っていきます。ご自身の膀胱の機能を信じましょう。
男性にもオススメ
男性が抱える排尿後のぽたぽた漏れや頻尿などに対しても、イントレや膀胱コントロールはとても有効です。
前立腺の肥大を抑え、尿道括約筋を健全な状態に保つことができれば、排尿障害を改善することが可能だと考えられているからです。
前立腺は、膀胱の出口に存在する男性にしかない臓器で、精液の一部を生産する働きをしています。
日本人の正常前立腺は約10~20g。平均すると18g程度の大きさです。その中を尿道が通り、周囲には尿道周囲腺(内腺)があります。この部分が腫瘍性に大きくなったものが「前立腺肥大症」です。
病理学的には前立腺の肥大は40歳代半ばから始まるといわれていますが、排尿障害などが怒るのは60歳以降であることが多いそうです。
イントレで骨盤底筋を動かし、血流を良くして前立腺を守りましょう。排泄ケア研究会において発表した男性へのイントレや膀胱コントロールの評価においても、効能ありといわれています。
男性の皆様もぜひ、一緒に取り組んでいきましょう。
前立腺の肥大を抑え、尿道括約筋を健全な状態に保つことができれば、排尿障害を改善することが可能だと考えられているからです。
前立腺は、膀胱の出口に存在する男性にしかない臓器で、精液の一部を生産する働きをしています。
日本人の正常前立腺は約10~20g。平均すると18g程度の大きさです。その中を尿道が通り、周囲には尿道周囲腺(内腺)があります。この部分が腫瘍性に大きくなったものが「前立腺肥大症」です。
病理学的には前立腺の肥大は40歳代半ばから始まるといわれていますが、排尿障害などが怒るのは60歳以降であることが多いそうです。
イントレで骨盤底筋を動かし、血流を良くして前立腺を守りましょう。排泄ケア研究会において発表した男性へのイントレや膀胱コントロールの評価においても、効能ありといわれています。
男性の皆様もぜひ、一緒に取り組んでいきましょう。